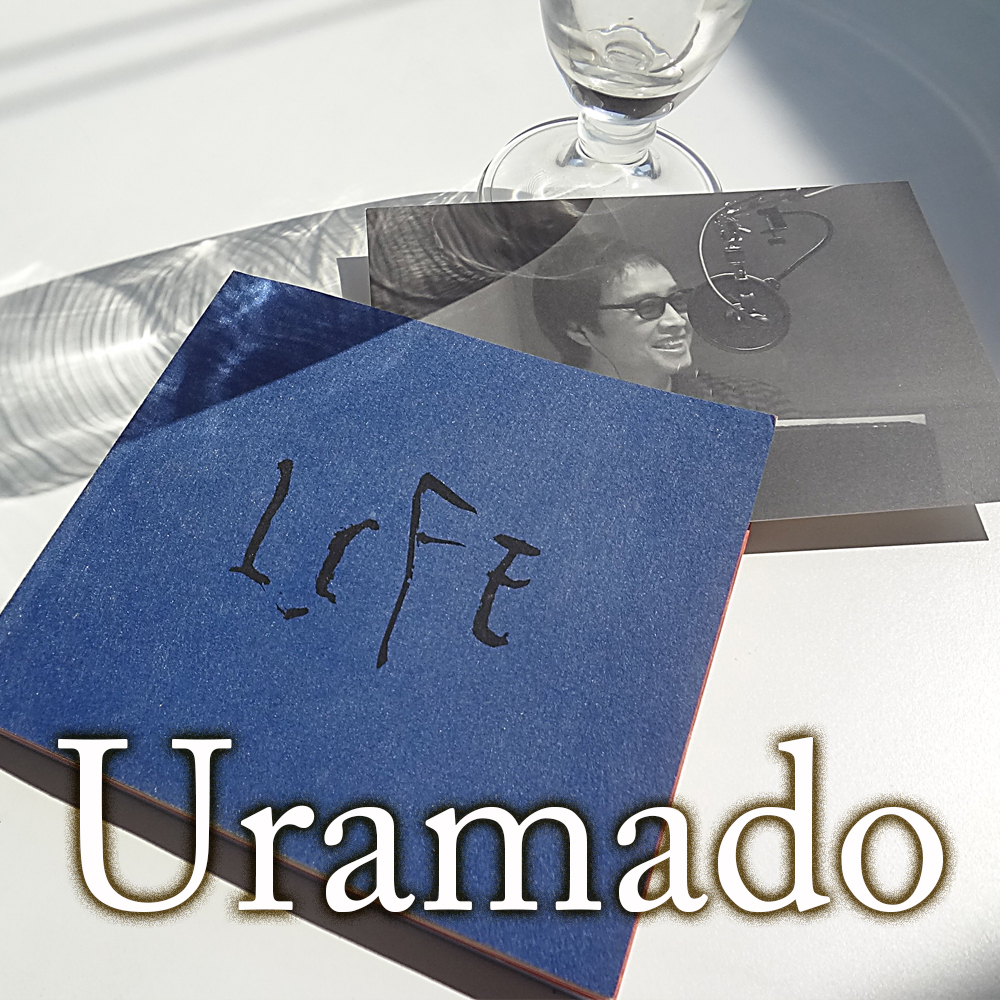Woo Baby
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「情熱」
音譜の行間に滲む不良性を求めて
イントロで思わず身体でリズムをとりたくなるようなギターのソロ。はーい、一緒に手拍子。コレに寄り添うように次々にキーボード、ベース、ドラムがjoinしていくところもご機嫌だ。そして、何と言っても拓郎の声には「恋する男の艶」がある。恋に溺れることの幸せの中に僅かの切なさが覗くようなメロディーも見事だ。間奏のギターのリフは、踊れない人でもついステップを踏みたくなるようなウキウキ感がある。ともかく歌手とバンドの円熟と余裕を大いに感じさせてくれる。・・・と今は心から思う。
しかし、1983年当時はどうだったろうか。森下愛子と思われる女性とのどっぷりとした恋愛が背景にあるこの作品を、好意をもっては迎えられなかった。メッセージのカケラもなければ、明日に向けて聴き手を元気づけてくれる言葉もない。スキャンダラスな恋に溺れる拓郎への残念感は、自分だけでなく少なからずの熱狂的ファンの不興をかこってしまったようだ。いわゆるマニアなファンの思いと拓郎の思いとが「すれ違う80年代」の極みの作品かもしれない。
そもそもラブソングを歌って叱られるなんて歌手は、吉田拓郎とボブ・ディランぐらいだろう(岡林信康を忘れていたが、とりあえず忘れたままにする)。評論家の中山康樹氏によれば、ディランは難解で気難しい哲学者のように見えるが、実はなーんにも考えていないとのことである。しかし拓郎は違う。たぶんあれこれ気に病むくらい考えている。ファンの要望と自分のやりたいことのズレには敏感に気づいていて、実はとても気にしている。しかしそれに振り回されていては、自分の音楽ができない。なので、敢えて「ファンなんか関係ない」「ファンだからってえらそーにすんな!」と何も考えていない傍若無人のフりをして振り切っているのだと思う。
しかし、時間もここまで経てば、ノーサイドである。ホントに優れた音楽をもう一度聴き直して、もう一度あらためて拓郎にホレなおそうではないか。そんな一曲でもある。
王様バンドから離れて約5年後の89年のツアーで演奏されたことがあった。最終日が東京ドームだったツアーだ。この時のバンドが悪かったということではない。この時も実力派ミュージシャンで固められていた。しかし、レコードの質感=恋するウキウキ感、恋に溺れた退廃感、不良感のようなものが出ておらず素っ気なかった。やはりあの質感は、不良おじさん集団であった王様バンドだけの「技」ないしは「体臭」のようなものだったのだろうか。たぶんあの方たちは、今も根は不良のままだろうから(笑)、是非もう一度再演してみてほしい。
2015.10/25