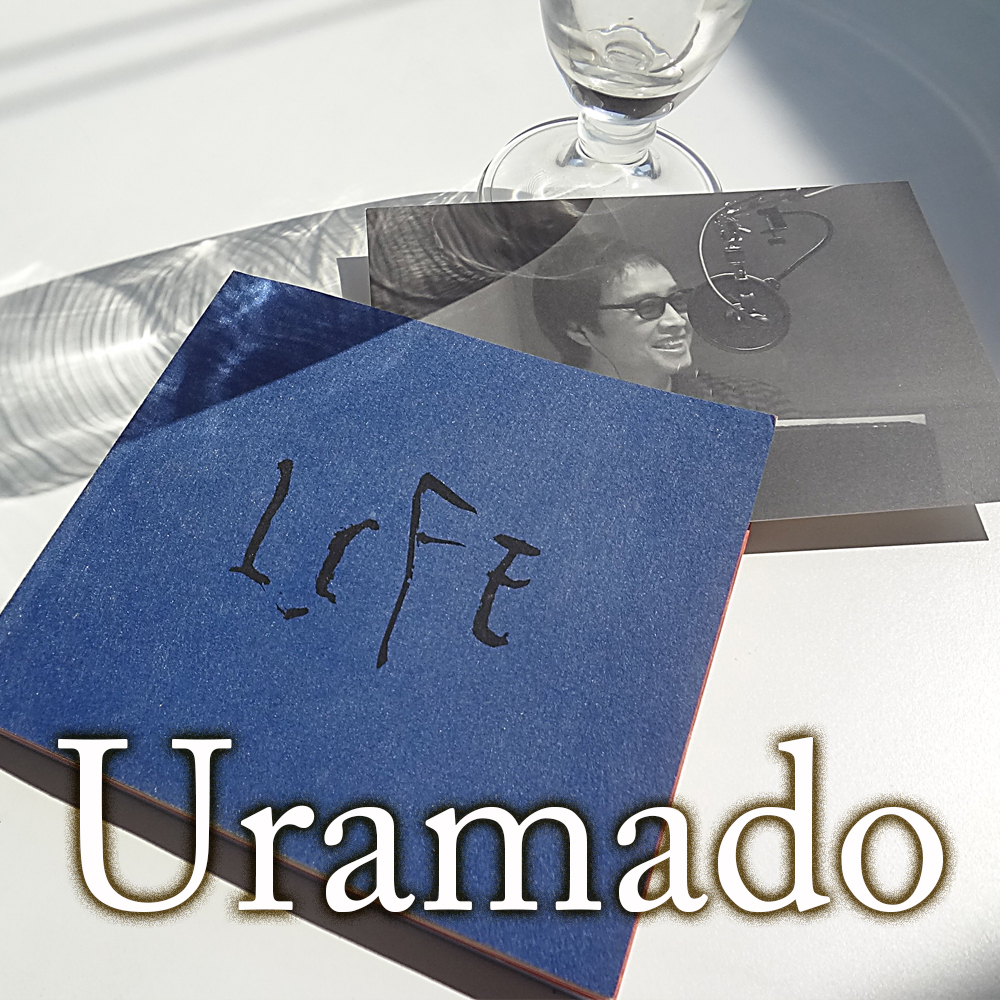SCANDAL
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「情熱」
愛でないものはあるはずがない
当時の吉田拓郎は文字通りスキャンダルの渦中にいた。今も昔も変わらないワイドショー的なスキャンダルだ。なのでこの作品や"男と女の関係は"を聴くとマイクを持った須藤甚一郎のあの将棋の駒のような顔が浮かんできて仕方ない。ということで世間的には拓郎のイメージは悪いなんてもんじゃなかった。しかもこの歌はまるでそんな世間やマスコミを挑発するような攻撃的な言葉が並んでいる。もう完全にヒールだったね。
一方でファンの私もこの作品を始めアルバム「情熱」全体に対してやるせない残念感があった。それは世間様と同調してスキャンダルがけしからん…というものでは断じてない。そもそも吉田拓郎の歴史はスキャンダルの歴史である。世間の悪口雑言のその中をどけ、どけ、どけと払いのけ、時に満身創痍になりながらも道を開拓してきたのが吉田拓郎であり、そこにこそ惚れたのだ。そんなカリスマヒーローだった吉田拓郎が、尖鋭なメッセージ性、カリスマ性を投げ捨ててを恋愛の唄に耽溺していることに対する失望だった。"二人で行こう、二人の国へ すべてを捨てて愛から始めよう"。この歌を屈託なく受け入れられたファンというのは当時どのくらいいたのだろうか。少なくとも私はもっとハードなメッセージをくれ!と怒りながら悶絶していた。
今にして思えば全く独りよがりな甘ったれたファンだったと思うし、拓郎は音楽ではなくカリスマ性のみを求められ不本意だったろうなと思う。このような「世間」,「拓郎」,「私のようなファン」という三者それぞれの思いがてんで違う方向を向いていた。見事にすれ違っていた。なんという不幸だろうか。85年に拓郎はつま恋で一旦音楽の第一線から撤退するのだが、このようなすれ違いの状況が全く関係なかったとは言えないのではないか。ということで自分としては、この曲を楽曲としてちゃんと味わうこともなく放置したままでいた。
この不幸なすれ違いの中で、私が見失ったものは、音楽の素晴らしさ、わけてもそしてラブソングの美しさだったと今は身に染みてわかる。あの時の偏見と先入見を取り払って聴けば、タイトなギターで始まるオープニングからご機嫌なロックナンバーである。これを支える王様バンドの真骨頂ともいうべき鉄壁のサウンド。歳月を経て聴くと実にカッチョエエ"ラブソング"とだったことに気が付くのだ。
当時は世間を挑発するようなヒールな歌詞にしても、こうして聴くと…何である、愛である。メロディ―やサウンドこそ対局だが"I'm In Love"としっかり通底している。世界を敵に回しても、クソガキなファンが文句たれようとも、たったひとりのために捧げた愛の歌。40年添い遂げた二人の今を観ると、至極のラブソングであったことに遅ればせながら気が付くのだ。
「レコードではおとなしかった」と拓郎も2020年の拓つぶで述懐している。この曲はワイルドさにこそ真骨頂があったという意味だろう。そういえば1985年One Last Night つま恋ではオープニングの"悲しいのは"に続く2曲目がこの曲だった。オープニングの高揚感をそのままグイグイとこの曲で引っ張っていったのを思い出す。
勝手ながら、歳月のこだわりを抜けて、至極のロックでありラブソングとしてもう一度会えるのだろうか。"Woo Baby"," I'm In Love"のように新たな命を得たように輝きだす…なんていう出会いがあったら両手を広げて迎えたい。あんときゃすまなかったけれど、ご機嫌なラブソングだねぇと小さな声で叫びたい。
2020.4.8