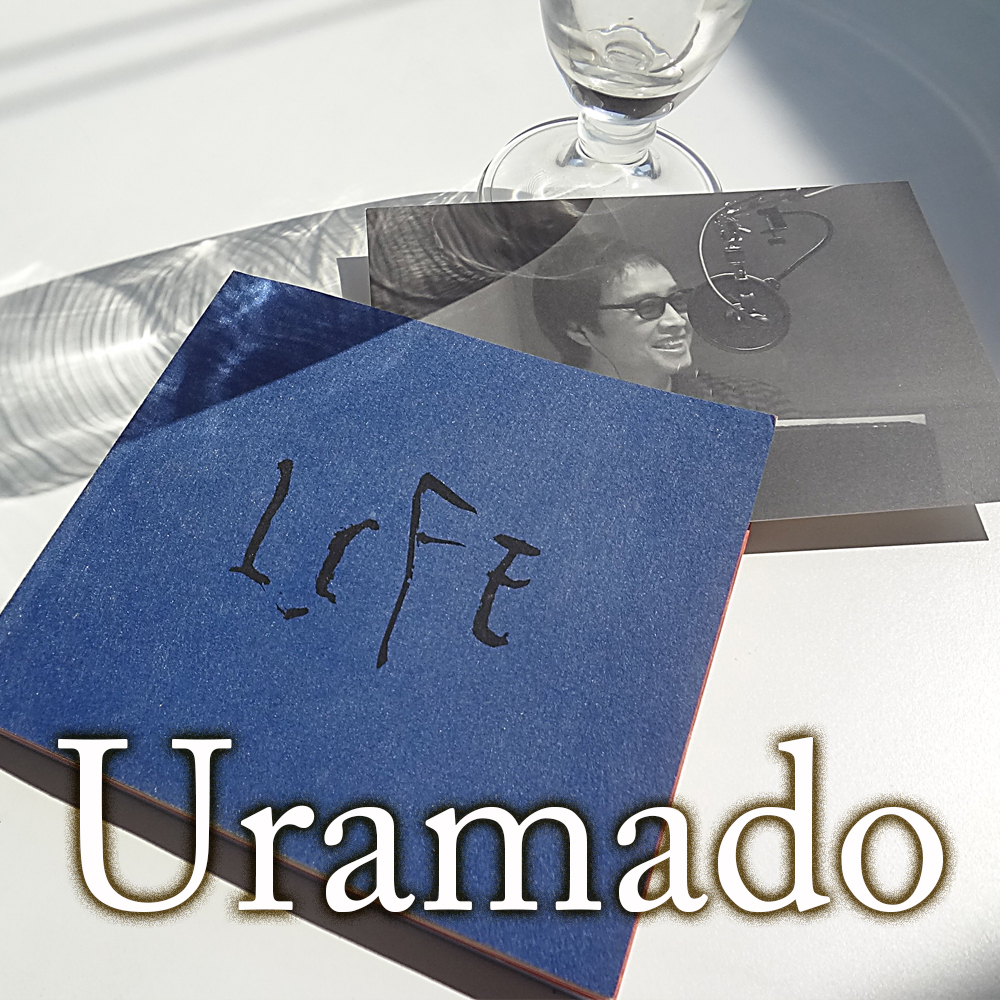ペニーレインでバーボン
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「今はまだ人生を語らず」/アルバム「TAKURO TOUR 1979」/DVD「Forever Young 吉田拓郎・かぐや姫 Concert in つま恋 2006」
飲んだくれと言うなかれ。それはバーボンを抱くという聖なる行為なのだから。
「ペニーレインでバーボン」。このタイトルだけでひとつの社会現象を想起させる。コレに対抗できるのは、オードリー・ヘップバーンの「ティファニーで朝食を」、千利休の「大徳寺で茶の湯を」くらいだろう。千利休は作らせていただいた。
かつて原宿の若者文化の象徴として「ペニーレイン」は眩しく輝いていた。あの頃の若者は、みな「ペニーレイン」を目指していたと言っても過言ではない。ビートルズの楽曲「ペニーレイン」にちなんでいるものの、もはや「ビートルズ」だろうが「ずうとるび」だろうが関係なく、まさに「吉田拓郎」の君臨する聖地として定着していた。そして音楽史のエポックの舞台ともなった。
作品としては、名盤「今はまだ人生を語らず」の一曲目。かつて、これほどまで鮮烈な一曲目があっただろうか。ついでに、間髪入れずに続く「人生を語らず」。かつて、これほどまでに扇情的な二曲目があろうか。これらの最初の二曲だけで、神盤決定だ。
「陽気に生きて行くことがみっともなくもなるよね」「お世辞を使うのが億劫になり、中には嫌な奴だっているんだよと」などこれまでの歌詞の常識を覆すような意表を突く砥ぎすまされた詞、エネルギッシュなメロディー、パワフルな演奏、そして神がかりのようなボーカル、これらがまさに固く撚りあって出来上がった頑丈なロープのようだ。そのロープに私たちも時代も、からめとられるようにしっかりと牽引されていたのだ。
例えば、沢田研二「勝手にしやがれ」の「バーボンのボトルを抱いて」は、「そんな時僕はバーボンを抱いている」からインスパイアされていることは間違いない。そうでしょう?天国の阿久さん。
演奏は、ドラムとベースは平野肇・融兄弟、ギター矢島賢、キーボード松任谷正隆、でスタジオ収録される。原曲は、74年の春ツアーでの弾き語り「今日もまたペニーレインで」。鬱々とした弾き語りのブルースが、かくもスピーディなロックンロールに「転生」する。そのレコーディングの時の思い出を記した平野肇さんの達意の文章はとても貴重だ(「僕の音楽物語1972~2011」)。
「予想を超えるパワフルな歌声が耳に飛び込んできた。字余りぎみの歌詞を投げつけるようにリズムに乗せていく。乗せていくというより、その歌詞にドラムとベースが引っぱられていく。」
「いろいろなタイプのボーカリストともやってきたけれど、段違いのパワーを感じた。しかも日本語がこれほど突き刺さってくるという驚き。」
「完璧にロックであり、ロックースピリッツに満ちた歌だった。」
「歌詞のコピーは非常に効果的だったと思う。そこにちりばめられた言葉と、それを吐きだすボーカルにシンクロしながらドラムを叩くことができた。」
「洋楽ばかり聴いていて、日本のアーティストを知らない自分を反省する機会でもあった。」
このレコーディング・メンバーでレコードそのままに生で一度だけ再演したのが、TBSテレビ「歌謡最前線」。個人的だが、私は、この時のテレビを観て雷に打たれて以来、こうなってしまった。手に汗握る張りつめた緊張感。どこにも隙がない。まさに平野さんの文章そのまま、礫のような歌詞に牽引される音楽と緊張感あるボーカルに打ちのめされた。
しかし90年前後を最後に、作品の公表が自粛され、その結果、神の如き名盤「今はまだ人生を語らず」は、廃盤となり、今日に至る。80年のインタビューだったが、拓郎は「オレのアルバムでは「今はまだ人生を語らず」が一番イイ」と認めている。その最高傑作が廃盤であることの不幸の深さ、わけても本人の辛さは測り知れない。一ファンの私とて、くだらねーアルバムが「日本音楽界の最高峰」とか賞賛されるたびに悔しくて眠れなくなる。ああ、この名盤をやつらにたたきつけてやりたい・・・おいおい。
既に「つんぼ桟敷」というフレーズは、雑誌「フォーライフ」創刊号の対談によれば、遅くとも76年当時には既に問題になっていたようで、それがなぜ90年になって自粛となったのか。社会の外圧なのか、あるいは拓郎側の主体的な配慮もあったのか、ともかく真相はわからない。拓郎も、そのいきさつを語ろうとはしなかったし、90年の男達の詩ツアー以来、ステージで歌うこともなくなった。
全くの推測にすぎないが、本人も言いたいことはあれども、この作品の本質とは関係ない差別・言論論争の主戦場になって、この作品が踏み荒らされることがいたたまれなかったのではないだろうか。名曲を封印した不幸の陥穽(あな)は、より良い新曲を作り続けていくことで
超えて行こうという「音楽家」としての静かな決意があったのではないか。
やがて2006年のつま恋。直前のラジオで、拓郎は、オープニングの一曲目を渾身のチカラで歌うと宣言した。一曲目はなんだ!?とファンは色めき立ったが、実に16年の沈黙を経ての「ペニーレインでバーボン」だったことで私たちを驚かせた。この作品が、決して死んでしまったわけではないこと、いや深く確かに生き続けていることを示してくれた瞬間であった。
歴史も遺恨も、あらゆることを蚊帳の外に置いて、つま恋を舞台に、バンドたちと楽しそうに歌いまくる御大の姿が、語りかけてくるものに耳を澄まし、目を見張ろう。
2015.8/21