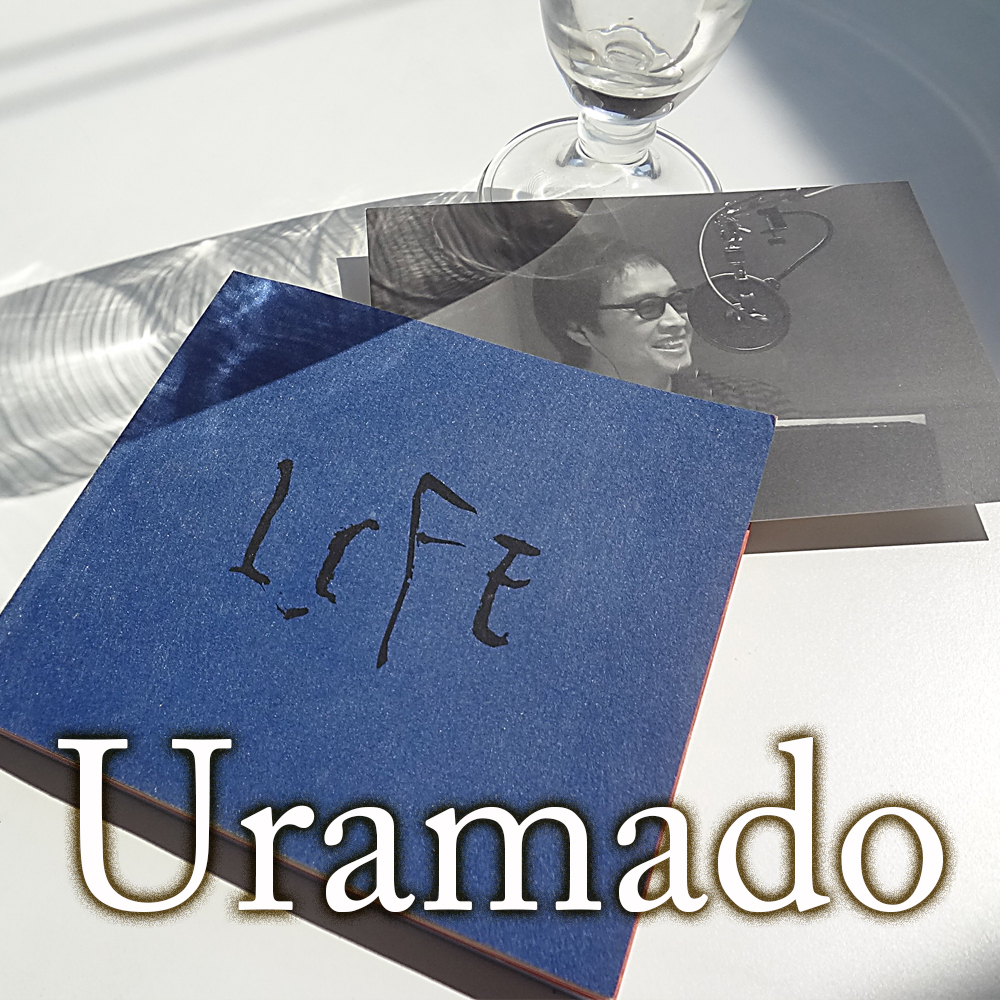大阪行きは何番ホーム
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「FOREVER YOUNG」/アルバム「吉田拓郎 ONE LAST NIGHT IN つま恋」/DVD「'85 ONE LAST NIGHT in つま恋」
早送りの走馬燈とあの人の立ち姿
自分の半生を正に走馬燈のように歌うこの作品。赤裸々だが、感情に溺れたり自己陶酔したりせず、淡々と自分の来し方を歌いこむ。歌いこむというよりも性急に言葉をたたみかけるさまは、まるで感情に足を取られないよう走り抜けてしまおうとしているかのようでもある。テンポよく流れていくような演奏もおだやかな川の流れのように心地よい。歌詞のフレーズは、簡潔で抽象的だが、ひとつひとつが深い歴史を背負っていることは私なんぞが言うまでもなかろう。
例えば「人を信じるはかなさが心の形を少し変えてしまった」と早口で歌われる詞には、金沢事件で世界中が敵に回った地獄のような経験が疼いているに違いない。「幸福という仮の住まいに子供の泣き声まで加わっていた」「真実を隠したまま旅に出た」というフレーズには愛する家族との身を切られるような別れが刻まれているのではないか。「優しさや思いやりを投げ出して二人は違うたびに出て行った」という自分の背負った罪からも逃げていない。その凝縮された歴史と時間が「家を捨てたんじゃなかったのか」という叫びでバーストする。拓郎は自分に向けて叫んでいるのだろうが、この叫びが聴く者の心までをも揺さぶってくる。聴くものまでもが、それぞれのここまでの旅路と通底するかのように「家を捨てたんじゃなかったのか」と自分にも問いかける。吉田拓郎だからこそ描き得て歌い得た、まさに身を削るような傑作である。御大とともにこの道をゆく私たちこそが分かち合える作品でもある。
何度も言うように80年代前半、恋愛に溺れ、メッセージ性が消えていく拓郎に多くのファンの不満があった。いわゆる拓郎とファンとの「すれ違いの80年代」だ。しかし、84年にこの作品が発表された時、もっというとこの作品を含むアルバム「FOREVER YOUNG」の一群の作品たち(「7月26日未明」「LIFE」等)を耳にした時、マニアなファンたちもさすがに唸った。「こりゃ名曲だ。オレたちの拓郎が帰ってきた。」と。
しかしこの時拓郎は、浅田美代子と離婚を決意し、翌年のつま恋でファンの前から消えステージを降りようと決心を結んでいたのだ。あぁ、どこまですれ違うのか80年代。あるファンが語っていた。「拓郎は離婚のとき、と不動産を買うときに必ず名曲を書く」けだし至言なり。先日(2011年)拓郎はラジオで不動産のローンの支払が終わったと語っていた。チャンスだ。「拓郎さんもうひとつ不動産買いませんか」と番組にお便りを出そう。
この作品は二度目の離婚のところで終わる。ご存知のとおりそれからも有為転変、拓郎の人生は続く。もしこれが「ロード」だったら、「大阪行きは何番ホーム第二章 再再婚編」「第三章闘病編」・・・と果てしなく続編を続けたかもしれない。
この作品は、「繰り返し、繰り返し旅に出ている」と歌いつつ最後に東京駅のホームで立ち尽くす拓郎の姿で終わる。ギターケースを下げて、ホームにうつむいて佇んでいる拓郎の孤独な姿が目に浮かぶ。そして続編なんかよりも、この姿がその後のすべてを能弁に語っている気がする。映画「ゴッドファーザーpartⅡ」のラストで、在りし日の家族の情景を想いだしながら、ひとり椅子に座っているだけで、鬼気迫る孤独を体現したアル・パチーノを思い出す。あの姿がすべてを語っておりその後の続編partⅢは作る必要がなかったともいわれている。御大のホームの立ち姿はそれと同じで実に象徴的なものに思える。
そしてこの歌がその後もコンサートで歌い継がれてきたことは記憶に新しい。中止となった無念のツアー「country」でも大切に歌われた。この時のMCで「ツアーの限界」を語った拓郎が「この歌もこれでたぶん最後だ」と言いながら万感の思いをこめるように歌われたことが忘れられない。もちろん御大とファンの音楽の旅はまだまだ続くのだ。
2015.10/4