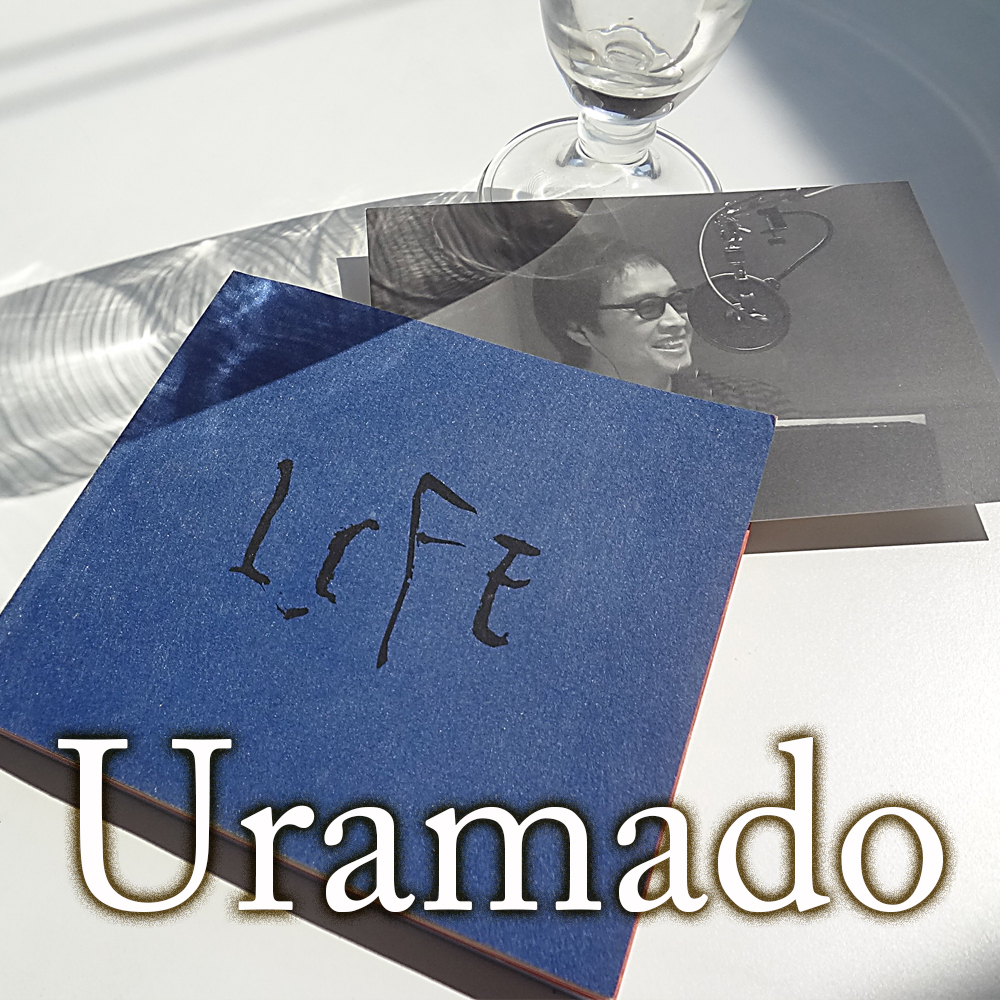オーボーイ
作詞 石原信一 作曲 吉田拓郎
アルバム「Long time no see」
オーボーイズ・ビー・アンビシャス
90年代前半。さまよえる拓郎。加速するファン離れ。世間から静かにフェイド・アウトしていきそうな危うい時期だった。「拓郎氷河期」「冬の時代」などと言われている・・って、私が勝手に言ってただけだ。しかし、この時期の「救い」は、石原信一の詞だったのではないかと思う。この厳しい冬の時代に何篇もの珠玉の詞を書き、拓郎とともに名曲を残した。
加齢ということは、何かから降りていくこと、ある種の負けの悲哀を味わうことだ。石原信一の詞はそんな現実から逃げずに、それでも微かに光刺す希望を見せてくれる。ボロボロなのだけれど、その中にだけ宿るカッコ良さを拾いあげてくれる。岡本おさみにも松本隆にもなかったことだ。かつて「挽歌を撃て」という迫真の拓郎ドキュメントをものにした石原信一は、他のどの作詞家よりも、「吉田拓郎」について分析と研究と体解を得ていたからではないか。どの作詞家よりも拓郎の魅力を知り尽くしていたからこそ、拓郎をこんな風に輝かせたいという愛情に満ちているような気がしてならない。
「俺はもう吠えたりしないよ」、「怒りをぶつけて叫びをあげて自分の弱さを誤魔化していた」、「おまえで歴史は変わりはしない」、「俺はもう踏まれていいのさ」
拓郎を知るものにとっては、かなりショッキングで自虐的なフレーズだが、その言葉の行間に浮かぶ「清々しさ」。何かから自由になって歩き出すような爽快感が滲み出ている。当然、拓郎にもこの思いは通じていて、この清々しさをきちんと伝えるメロディーでありアレンジであり演奏になっている。ゆったりとした風格ある曲相が、心地よい。西海岸の同世代のミュージシャンとのセッション、そしてバハマでの録音も存分にその曲相が生かされている。少しせつないが、生きて行こうじゃないかと、聴く者にも静かな力が湧いてくるようだ。
音楽に回帰して、ゆったりと動き出す吉田拓郎を感じさせてくれる。その原因は拓郎の才能であり、ミュージシャンの力量であり、バハマという環境であるかもしれないが、バハマのコンパスポイントスタジオのキッチンで詞を書きながら、みんなのためにインスタント・ラーメンを甲斐甲斐しく作っていたという石原信一のおかげも大きいのではないかと思う。
2015.4/26