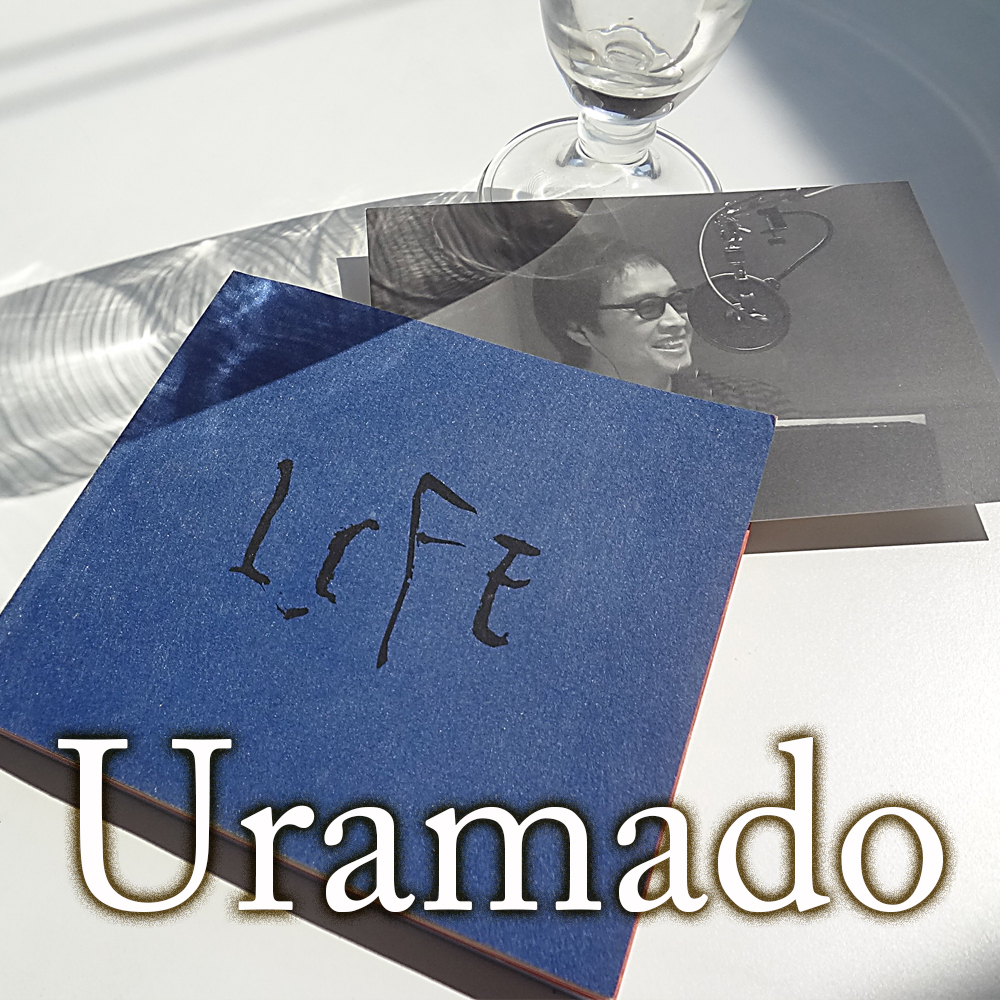むなさしさだけがあった
作詞 田口淑子 作曲 吉田拓郎
アルバム「よしだたくろうLIVE'73」
廃墟の街に響く至極のボーカル
名盤「ライブ’73」に収められ、「春だったね」と同じ作詞者田口淑子の手になるこの作品。田口淑子は謎の人だ。「春だったね」は、もともと素人の応募作品で、女学生が書いた詩だったという説もある。また、ファッション誌の編集として著名な編集者の方ではないかなど諸説ある(同姓同名だからか)。とにかくその後に柏原よし恵などの作詞の後に、80年代初頭には、作詞の世界から忽然と消えたままだ。
拓郎関係では、全部で3作の詞がある。「春だったね」と天地真理に提供された「さよならだけ残して」、そしてこの「むなさしさだけがあった」。たった3作だが、それぞれの詞の様相が全く異なる。別れた女性を思う男性の疼くような思いを描いた「春だったね」。ドキドキしながら彼氏に思いをしたためる乙女チックな「さよならだけ残して」。これらの作品と比べて「むなしさだけがあった」は、政治闘争や事業に挫折し、傷つき疲れ果てた中年の失意のような心情が描かれている。こうも違った視点から説得的な詞が書けるものだと驚くほかない。どんな人なんだとますます気になる。
この作品はもともと「その日、その日」というタイトルのもとに、ほぼ異なったメロディーで新六文銭によって演奏されたのが出自である。試作品だったのか。それが、ライブ’73に至って、現在のような完成作品として転生し、歴史に残ることとなった。そしてこっちの方が新六文銭の原曲よりも格段にスバラシイ。
心に哀しく響く石川鷹彦のギターの音色に胸かきむしられる。ビッグバンドのサウンドは、しっかりとした塊になっていて、しかし大仰にならずストリングスの音色に誘われるように優しく漂う。
「涙の出るほど淋しいひとりぼっち」「涙で崩れ落ちた砂の家」「風だけが強く吹く」「荒れ果てた街の角」と言う詞の世界は、まるで廃墟の街にひとり佇んでいるような荒廃した景色を見事に描き出して行く。
そして圧巻は、「どこに行っても同じなら もうこれ以上傷つくのは嫌だよ」「荒れ果てた街の角何も思わず立っていようか」との悲痛な嘆きの中に突き放されるように終わってくサビだ。この最後にかけての詞・メロディー・歌の三者の魂に響くようなインパクトと言ったらない。ガラガラになる寸前の掠れた声質の拓郎のボーカルは、力強くも哀しみに満ち溢れている。これは、やはり半年前に地獄を見てしまった男の怨念が濃いスパイスのように効いているからに違いない。この時の拓郎だからこそ作り得て、拓郎だからこそ歌い上げられた傑作というほかない。言うまでもなく挫折と悲しみは、種類や程度の違いはあれ、人それぞれに襲ってくる。天を仰いで立ち尽くすような時間。そんな時のために用意されたような作品として息づいている。
ここまでの繊細な哀しみを見事に描き上げているライブ73の拓郎とビッグバンドのコラボの凄さを思わずにいられない。この傷つき尽くしたような情感の見事な描き出しが、このアルバムを名盤たらしめているひとつのチカラだと思う。
2016.1/17