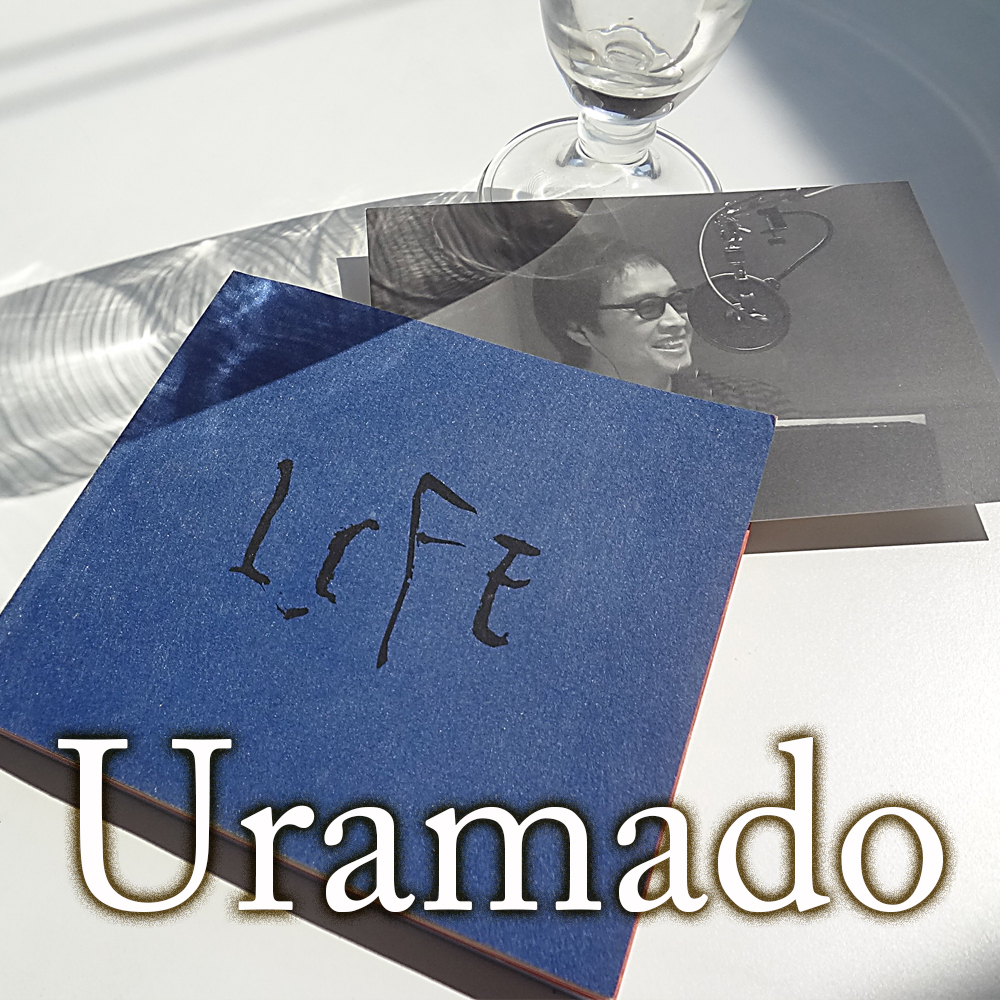メランコリー
作詞 喜多條忠 作曲 吉田拓郎
アルバム「ぷらいべえと」
電話の声は新幹線だとウンと速い
言わずと知れた梓みちよに提供した1976年のヒット作品。翌年に早々にアルバム「ぷらいべえと」に本人歌唱が収録された。原曲は、74年の「二人でお酒を」の大ヒットでアダルト路線が開花した梓みちよに不可欠のレパートリーとなった。
梓みちよは、当時から既に女帝のような貫禄があったし、もともと中尾ミエ、伊東ゆかりらと同様、御大にとっては、かつての憧れのスターで頭が上がらないところがあったようだ。歌唱力全開で歌う梓に、あまりうまく歌いすぎないように頼む御大に「変なの、アンタたちの歌」と毒づき、ステージで譜面を見ながら歌うという御大を「アンタ自分の歌くらい覚えなさいよ」と叱りつけたなど御大受難のエピソードに事欠かない。しかし、この梓みちよの歌唱力の素晴らしさは、この作品の命脈のようなものといっていいだろう。かくして日本歌謡界においても不滅のスタンダード作品となった。
そして忘れてはならないのが、作詞の喜多條忠だ。「神田川」「赤ちょうちん」という青春フォーク路線からの脱却に苦悶していた喜多條。私生活でも男一人で幼子を抱えて大変だったらしい。そこに拓郎からの仕事依頼の呼び出しがかかる。しかし、呼びつけておいて拓郎は「梓みちよの大人の歌詞の依頼が来てオマエに頼もうかと思ったけれど、オマエにゃ無理だよな。松本隆に頼もうかな。」といきなり不遜な態度に出たそうだ。御大ならやりかねない。この挑発的な依頼に「やりますよ、やりゃあ、いいんでしょ」と応戦したという。
そうはいっても大人の女性の詞というテーマに苦悶する。そして男ヤモメだった喜多條が、子どもだった娘と公園でオウムを見た時のエピソードから「人の言葉が喋れる鳥」のプロットが生まれ、ようやく詞が完成し、拓郎側に提出した。その後のある日、新幹線で移動中の喜多條に、突然、新幹線車内電話で呼び出しがかかる。携帯のない昔、車内呼び出し電話ってあったよね。電話の主は拓郎で、こう告げた。「オマエ凄い詞を書いたな。俺のメロディーは負けた。」。その後、実際に拓郎は、別のいろいろな機会に「メランコリーは、詞の勝ちです。僕のメロディーが負けました。」と語っているのを自分も何度も耳にした。
拓郎は絶賛の言葉を新幹線車中の喜多條に届けたのだった。電話の声を聞いた喜多條は車中で男泣きに泣く。作詞家としてのスランプにあった苦しさ、拓郎の挑発的な依頼の時の悔しさ、いろんなことが混然一体とこみあげてきて人目をはばからず号泣したという。そう語る喜多條の様子をテレビで見ながら、私も家人があきれるくらい泣いた(笑)。厳密に言うと喜多條忠に共感したのではない。素晴らしい詞であることを、新幹線の電話を使ってまで伝えようとした御大の心に泣いたのだ。フツーは電話が、つながる場所に着くまで待てばいいじゃん。でも、喜多條に早く話したい、移動中?新幹線?、いいや待てない、えーい呼び出そう!、そうまでしても絶賛の気持ちを届けようとする拓郎の素晴らしさ。私たちファンは誇りと感動をもって胸に刻みたい。
詞に負けたというが、御大の謙遜であって、御大のメロディーも秀逸だ。成熟した安定感あるメロディー。前半の悲愁に満ちた切なさが「それでも乃木坂あたりでは」で陽転して立ち上がっていく構成も見事だ。舞台裏のエピソードが豊富なけれども、やはり作品本体の素晴らしさをよもや忘れはすまい。
2015.12/5