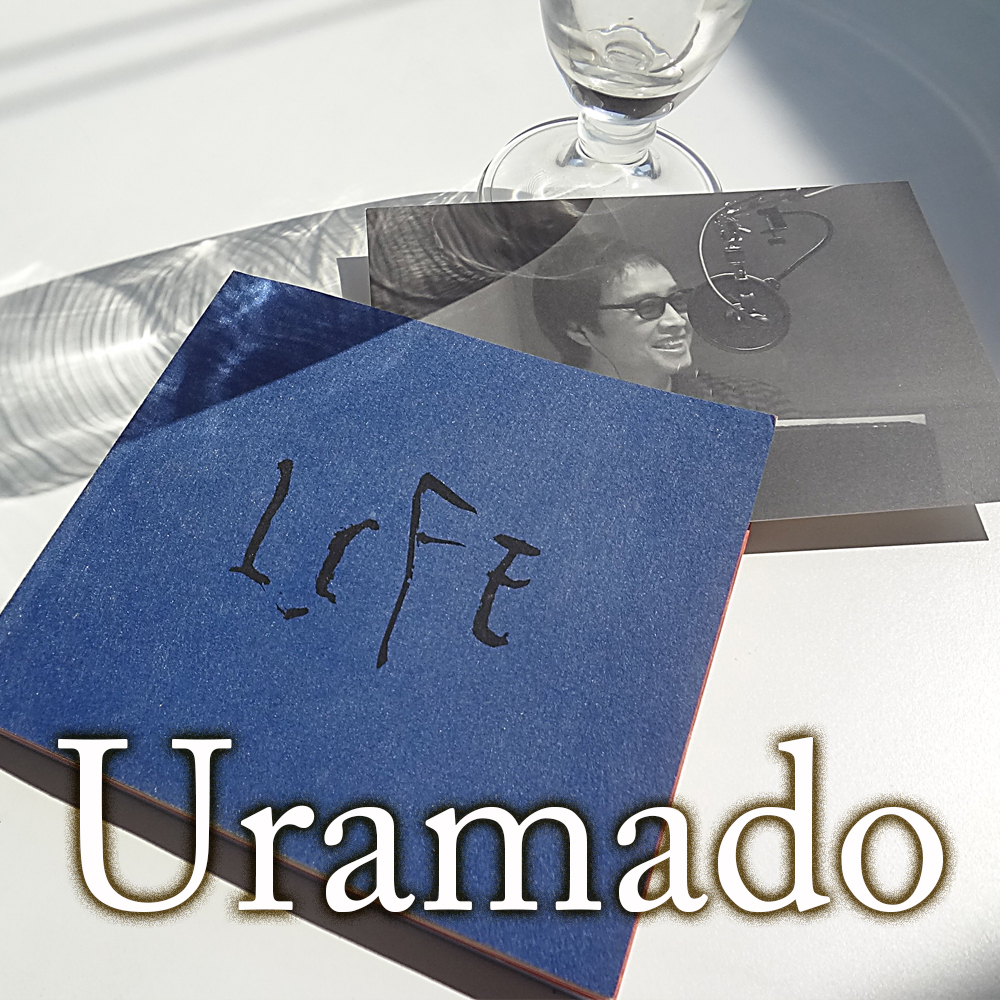Life
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「FOREVER YOUNG」/アルバム「吉田拓郎 ONE LAST NIGHT IN つま恋」/DVD「 ONE LAST NIGHT in つま恋」
Life is a lost voyage home
80年代の最高傑作とも評されるアルバム「FOREVER YOUNG」。その中でもこの作品は「大阪行きは何番ホーム」「7月26日未明」と並び名曲の誉れ高い代表作だ。しかし、そういう賞賛の言葉がどこか上滑りに思えるほど、この作品には深い悲しみが満ちている。「僕は間違っていたのだろうか」。あの意気軒昂で傲岸にも見えた吉田拓郎の苦渋のつぶやきから始まり、聴く者が身に詰まされるような絶望感が滲む。
元「猫」で御大のディレクターを務めた常富氏が、2014年の田家氏とのラジオの対談で、80年代中盤の御大との日々を切々と語ったことがあった。アルバム「マラソン」「情熱」の頃、おそらくは「あいつの部屋に男がいる」「I’m In Love」という恋愛路線シングルに対して、常富はマーケットサイドの人間として、「ファンはこういう曲を望んでいない」と厳しい進言をした時、御大は「俺はファンのために作っているんじゃない」と激怒したという。「そんなこと言ってもらうためにお前をスタッフにしたんじゃない」という御大の無言の怒りに、常富はアーティスト出身でありながら企業サイドに回っていた自分を悔いる。
そしてその翌年、御大は、離婚し、40歳で歌から身を引くことを逡巡していた時が「life」の制作時期と重なる。御大はある日泥酔し「常富、オレを何とかしくてれ」と弱音を漏らし、常富は「あんな拓郎を初めて見た」とのショックを隠さなかった。常富にとって「life」はそういう曲だという。この悔恨に満ちた述懐は涙なしには聞けなかった。
この時の御大の真意を考えることは、しょせん下種の勘繰りの域を出ない。しかし、下種の勘繰りに執念を燃やしてこそのファンである。
吉田拓郎にカリスマ性とイベンターとしてのスタンスを求めるファンや世間。しかしスキャンダルな恋愛に耽溺した作品を歌う御大は堕落した英雄のように評されることも多かった。自由に音楽をしたい御大とファンや世間の過剰期待との不幸なすれ違いは深まっていた。
そして離婚。御大は、離婚のプロのようにいわれるが、その相手と添い遂げられなかったことこそが人生の最大の挫折と後に語るように、その深い挫折感は、ファンが想像する以上のものだったと思う。さらに現場でのミュージシャンとの不協和音の悩みも語っていた。
おそらく御大は、ファンや世間、家族、そして仕事現場というすべての場面が閉塞するような身の置き所の無い哀しみと絶望の中にあったに違いない。そのたどり着く果てに、40歳まではジョンレノンの墓参りのつもりで歌い、そのあとは第一線から退くという「つま恋85のone last night」があったのだと思う。
吉田拓郎の作品群には、その時々でどうしようもない地獄を見たり人生の絶望を背負ったりしながら、うねりの中を進んでいくストリームのような唄がある。「流れる」「明日に向って走れ」「マラソン」そしてこの「Life」などなど。
しかし、この「life」にはもはや「流れる」「マラソン」のようなドラマチックなレトリックやベールもなく、ひたすら剥き出しのスピリットそのものが綴られている。それだけ傷口が生々しい。愛を巧みに操る輩がはびこり、一人じゃ何もできない衆生が我が物顔でルールを押し付けてくる。そして少数派の自分を潰そうとする。こんな世の中に負けてはならないという気概と、どうにもならない諦念と疲労感の間で苦悶する。名曲でありながら、あまりに痛々しい作品に仕上がった。
音楽的にはアルバム「FOREVER YOUNG」のバージョンが美しい完成版だ。しかし、圧巻は翌年のつま恋のライブだろう。白々と明けゆくつま恋のステージ。御大の荒れたボーカルを深みのあるサウンドが静かに寄り添うように包み込む。王様バンド最後の仕事だ。ステージに佇み、身体をよじって歌う御大の姿とともに刻みつけておきたい。
私たちはこの愛と絶望のストリームをやがて自分の人生にも重ねあわせ、それぞれのlifeを思いながら、御大との旅をつづけるのだ。
2016.4/23