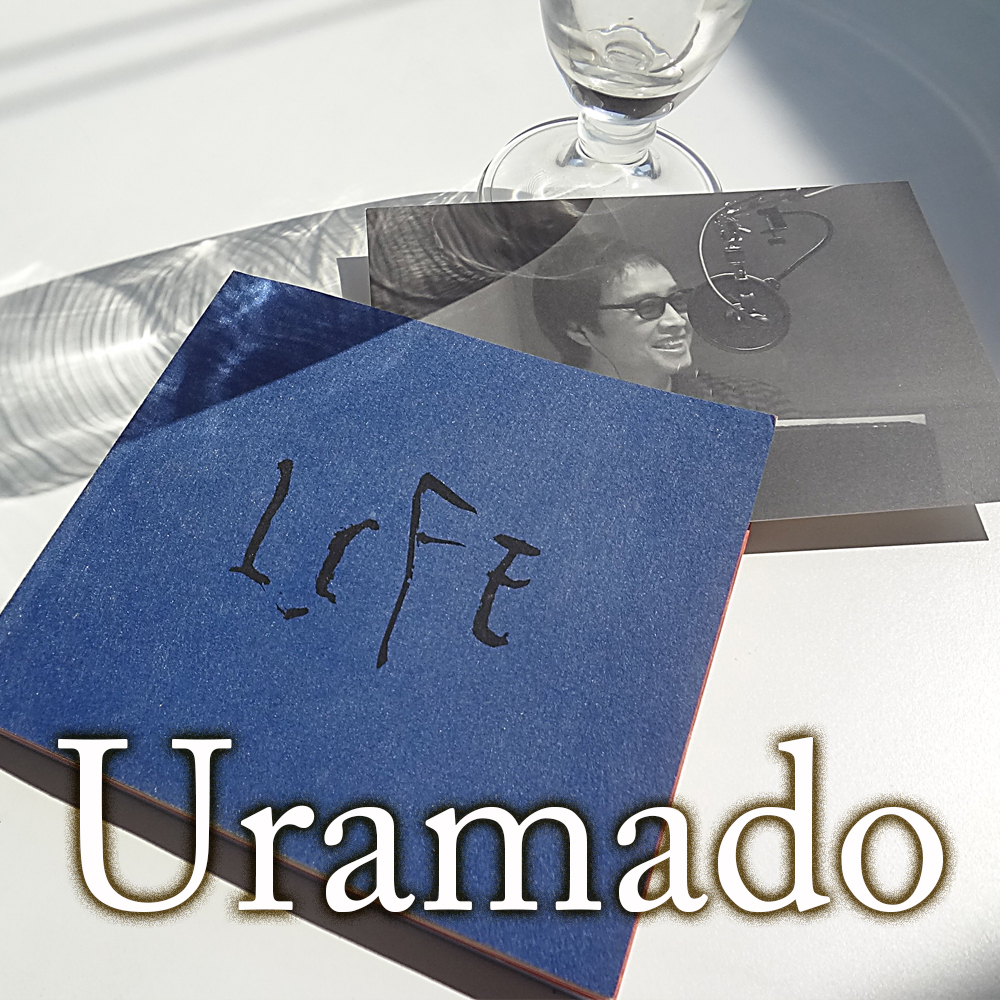今夜も君をこの胸に
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「マラソン」/アルバム「吉田拓郎 ONE LAST NIGHT IN つま恋」/DVD「85 ONE LAST NIGHT in つま恋/
今夜も君に懺悔して
あくまで個人的な話だが、好きでなかった作品、気にもとめなかった作品なのに、幾年月を経てある日名曲であることに気付いて愕然とすることがよくある。自らの不明と不覚を反省することになる。こんな風に「すべての御大の歌に懺悔しな」シリーズともいうべき作品群がある。
アルバム「マラソン」に収録されたこのラブソングは、1983年から84年にかけてのコンサートの定番のオーラスナンバーとしても記憶に残っている。しかし当時はアンコールでこの作品のイントロを聴くたびに「ああ、またこれかよ…」とトホホな気分に沈んだものだった。それはこの作品のせいというよりも、コンサートの最後は「人間なんて」や「アジアの片隅で」のような「燃焼発散系」でなくてはならないという強い思い込みからだったと思う。
毎回、御大の熱いメッセージを期待してライブに向かうものの、スキャンダラスなラブソングばかり聴かされてしまうがっかり感と肩透かし感…そのファンとしての行き場のない思いが、この作品のイメージにコンソメ・ブイヨンのように結実してしまっていたように思う。
しかし、そんな思い込みだなんだを遠く離れて、聴き直すと今さらながら至極の一品だったと思う。軟弱な歌と悪態をついたが実は成熟した大人の甘いラブソングであることにようやく気付く。すまなかったな…御大と殊勝な気持ちになったりもする。
イントロの軽妙でおしゃれなギターワーク。ライブでのロングバージョンでは、青山徹の静かなソロから始まり、まき散らかしたようなフレーズが収束してお決まりのフレーズにつながる粋なはからい。まさに青山徹の独壇場。間髪を入れずに”窓からあふれる星の数…”と御大の歌が滑り出すとたちまちこの歌の世界に引き入れられる。
言葉は少なではあるが、ゆとりを湛えた大人の目から描く恋愛の景色。御大の場面の切り取り方が、また甘く絶妙なラブ・ワールドである。シンプルながらたゆとうような甘いメロディー。特に間奏のギターのブリッジが特筆ものの美しさだ。青山徹と御大がステージでアイコンタクトしながら気持ちわさそうにツインギターを弾く姿が浮かんでくる。
曲の大半は“今夜も君をこの胸に すべては流れる時に乗り”というキーフレーズとキーメロが粛々と繰り返されてゆく。このリフレインが、ちょうど♪人間なんてラララ ♪ア~ジアの片隅でと同じくひとつのグルーヴを描き出す。ライブが終わった帰り道、前を歩く人が「ああ。♪今夜も君をのフレーズがどこまでも追いかけてくるようだ…」と呟いていたのを思い出す。それは”人間なんて”や“アジア”のような燃え立つものではなく、恋愛という無防備におだやかでやさしい快楽の世界に私たちを連れ出してゆく。御大のチャーミングなボーカルは文字通り魔法にかけられるような不思議なオーラがあって、大海をゆらゆらと漂うような心地よさがある。ああこのおだやかな海に身を任せていつまでもいつまでも漂っていたいとまで思えてくる。小品ながら、夜空に満ちるような独特なワールドというスケールを感じさせる。
初お披露目の83年の春ツアーの時は、なんじゃこりゃ?ぬるいラストだなぁということ以外特別何も感じなかったが、この歌の演奏とともに武道館には、星屑の照明が広がっていた。御大が描こうとしていた世界がそこにあったのかもしれない。そして今日までで最後のライブ演奏となったつま恋85。気持よさそうにこの作品に身をゆだねる御大がいた。♪…男と女の事はわかるのさ…イェーイ…今夜も君をこの胸に…。このイェーイでベストテイクに勝手に昇格してしまう。
なるほどただのガキだった自分にこの作品は理解しえなかっただろうとしみじみと思う。ともかく、いまいちどステージで懺悔の気持ちもこめてしみじみと聴きたい一曲である。
2017.2/5
そして前回の演奏から実に30年以上も経て、もしかしたらこれが最後のライブかもしれないというLive73yearsの大舞台にオーラスという定位置で帰ってきた。
ラジオでも事前に「最後の曲で今一番やりたいのが、今夜も君をこの胸に。僕と鳥山と渡辺格のトリプルのギターソロそれでお別れしようかと思う。(第90回 2019.1.20)」「 このギターを弾いたら、深々とお辞儀して投げキッスでステージを去る「もう会えないかもしれないな」なんて感じでどうだ。(第91回 2019.1.27)」と語っていた。なので予告どおりの展開となったが、それでも毎回、胸わしづかみにされる素晴らしいラストチューンだった。退場前の万感溢れる拓郎の姿は誰もが忘れられまい。上手、下手、真ん中と深々と頭を下げ、投げキッス、お手振り、ありがとうと叫ぶ。ありったけの深謝を何回も何回もていねいに客席に投げかける。この魂のこめられたレベランスとこの曲はもう不即不離に一体化していた。
何度でも書くが、かつて若い頃、さんざん悪態をついたラストである。しかし拓郎もこの歌もそんないわば放蕩息子のような私に叱責も拒絶もせず、ひたすらやさしく包みこんでくれた。コンサート会場を後にして、コンビニで買った缶ビールで祝杯を上げて飲みながら歩く帰路の道すがら、この歌は背中を手をあてて送り出してくれるかのように頭の中を回っていた。今にして思えばこの曲以外のラストはなかったとすら思う。
三人並んでのトリプルギターソロが定番だったが、初日だけは鳥山と山田が後ろにススっと退いて、拓郎だけにピンにライトがあたった。たぶん、奥ゆかしい拓郎はバンドなんだから三人一緒で…と修正したのだろうと思う。しかしこのピンライトのギターソロ、これはこれで冥土の土産ものくらいに感動的なシーンだった。
そもそもたぶん疲労困憊で体力もさんざん消耗しているであろうステージの最後の最後に、こんな大事なソロをもってくるという拓郎の凄さにあらためて感服する。
ラジオでの発言によれば、この曲はロッド・スチュアート「今夜決めように」インスパイアされて作られているとのことだ。あっちも名曲だが、こちらも遜色はなく勝るとも劣らない。“窓から溢れる星の数”~もうこの冒頭の言葉とメロディーの展開がもう天才である。ここだけでもういきなりクライマックスだ。いつまでも心の中で心地よく揺れる"今夜も君を…"のリフレイン。
星空の下、この歌に送られながら愛する人とどこまでも歩いてゆきたい…なーんて、こんなボロボロのおっさんすら、そんな甘美な気分にさせてくれる。すべては流れる時に乗り。そう、それがすべてだ。
2019.9/28