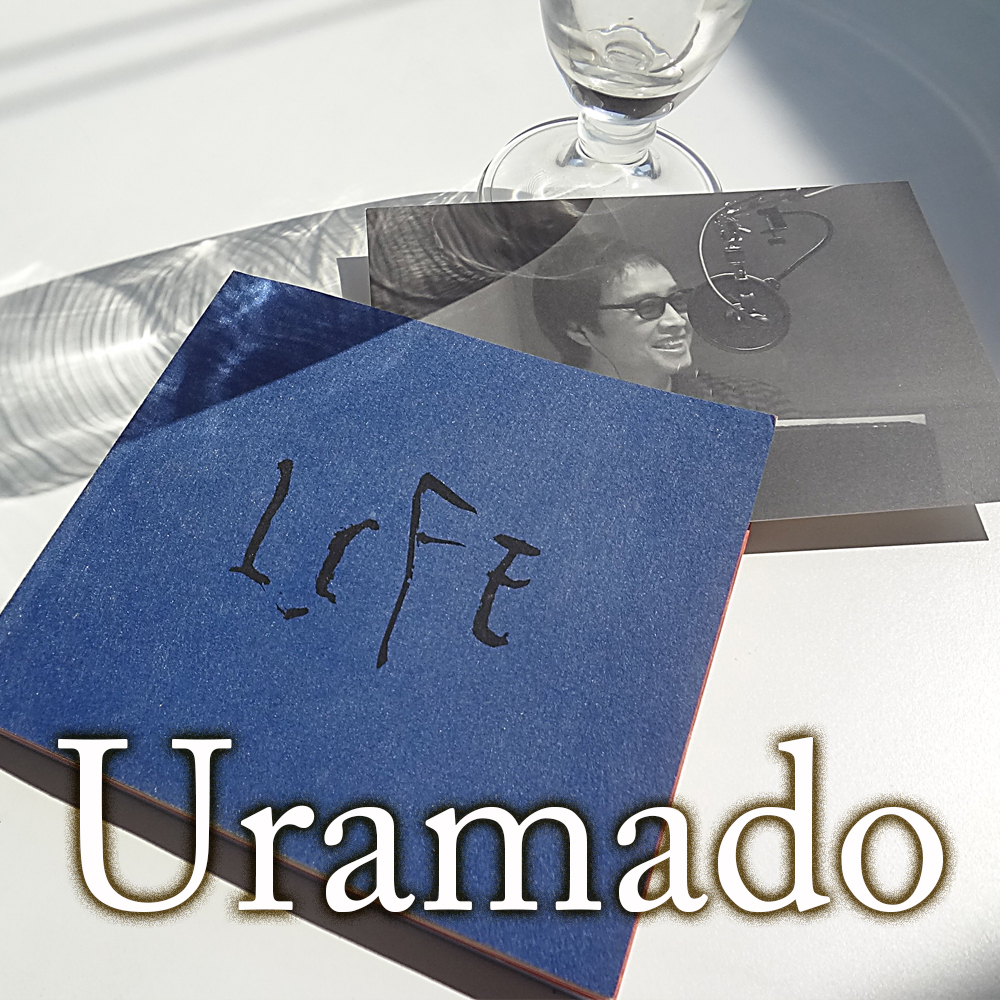この指とまれ
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「無人島で」/アルバム「王様達のハイキング IN BUDOKAN」アルバム「吉田拓郎 ONE LAST NIGHT IN つま恋」/DVD「 ONE LAST NIGHT in つま恋」/
握手する右手と戦う左手
リアルタイムでこの曲を聴いていたファンには、この曲を耳にするだけで条件反射のように人差し指を上げてノってしまう人も多いのではないか。それほど吉田拓郎の魂(スピリット)の体現された一曲だ。
初めて発表されたのは81年体育館シリーズ。なんとオープニング一曲目であった。一曲目に未発表の新曲をぶちかましてくるのは吉田拓郎ライブの中でも前代未聞だった。前奏に合わせてステップを踏みながらステージに現れた拓郎。初めて聴く曲にもかかわらず観客は皆スタンディングで実にゴキゲンでノリノリであった。その後同年秋のアルバム「無人島で・・・」に収録された。
この熱いノリの要因は、やはり抜き身の刀のような率直な詞のパワーが大きい。「キミの周りは変じゃないか?あいつはいつもの笑顔でいるけど。胸の中にまたひとつヤバいこと隠してる」「友達ヅラして手招きするけど」・・平穏に見える日常に潜む欺瞞にいきなり殺気をもって切り込んでくる拓郎。
この作品が発表された80年代初頭、拓郎の後発世代の「ニューミュージック」は一大勢力として席巻していた。このサイトは公式でもなんでもないので言い放ってしまうが、この詞は、そこに君臨していた「アリス」の「ハンド・イン・ハンド」に向けられているに違いない。「ガキの遊びじゃあるまいに」とは、みんな仲良くお手々をつなぐ「ハンド・イン・ハンド」を指している。
当時「シアターフレンズ運動」というプロジェクトがあった。アリスらミュージシャンが旗振りの広告塔になって「夢のコンサート会場」を作ろうと多数の賛同ミュージシャンを集め、そのための集金コンサートや募金活動を進めていた。みんなで仲良く手をつなぐ「ハンド・イン・ハンド」はその運動の象徴だった。
しかし実際には背後に企業や投資家など多くの良からぬ思惑が蠢いており、結局この運動は後に挫折する。吉田拓郎は当初からこの運動の欺瞞を指摘し反意を示していた。賛同ミュージシャンの数は圧倒的で、義理もあったのかユイからも南こうせつ、長渕剛らが参加していた。表立ってこの運動に反対していたのは拓郎以外ではタモリ(当時はまだまだマイナーだった)くらいであり、むしろ世の中の流れからは、みんなの夢に水を差すとして、逆に拓郎が非難のマトにされるような孤立無援状態だった。
美名のもとに音楽が商売のたくらみに利用される。そこに皆が右へ倣えをする。そんな状態に拓郎は我慢がならなかったのだ。拓郎は、そんな世の中の大勢に背を向けて、オレは先に行くよ、一緒に行くもの「この指とまれ」というのがこの歌のテーマだ。
そう思ってあらためて詞を見るといろいろなことが腑におちる。「信じることは義理じゃない、人の自由って何だったい?」「操るつもりが気づいたら不自由で」「言葉巧みなヤツら」「出まかせ言うな 愛など語るな」「オイラとにかく大っ嫌いだね」「甘いケーキは食えないよ」「オイラお先にちょいとごめん」と1人旅立つ拓郎。
しかし、たぶん拓郎もその後、歌うたびにハンド・イン・ハンドの顛末を思い浮かべていたとは思えない。そういう小さな話ではなく、世の中の体制の流れに潜む欺瞞、それに対峙する心の叫びの歌として昇華させていったのだと思う。また世の中の流れに関係なく、自分は断固ひとりで行くんだと孤独を背負い込む決意を胸に刻んでいたのかもしれない。だからこそ今もなおこの作品が普遍的な名曲として残っているのだろう。
幾星霜を経て、2006年のつま恋で「懐かしいけど」と断って実に久々に歌われたのも記憶に新しい。拓郎は忘れちゃいなかったのだ。もはや「シアターフレンズ」も「ハンド・イン・ハンド」も消え去ったし、ぬぅあんと2014年には谷村新司と御大は仲良く襟裳岬をデュエットしていてびっくらこいたものだ。もっと驚いたのは、ライブ直前、フォーラムの客席に現れた谷村新司に客席が総立ちでスタンディングオベイションしたシーン。頑迷固陋な自分を思い知ることになった。全ては過去のものになっていくが、この世に渦巻く新たな宿敵は今もこれからもたくさんあるに違いない。そんな時に拓郎のスピリットの結晶として、いつも心に備えておきたい一曲である。
2016.2/20
拓郎は2019年のラジオでナイト(第96回)で「この指とまれ」は“ハンド・イン・ハンド”や"シアターフレンズ運動"のことを歌ったものではない、それはネットの嘘だと苦言を呈した。また2019年7月28日の拓つぶのLive73yearsのライナーノーツでは、この曲とハンド・イン・ハンドの関係については「断じて!ない!」とまで明言した。この本人の魂の叫びを前にすると、もはや他の答えはない。
但し"この指とまれ=ハンド・イン・ハンド"説は、根拠のない嘘、妄想ではない。例えばひとつには雑誌「ミュージックマガジン」1981年12月発売(82年1月号)の拓郎本人のインタビュー(1985年に単行本「俺たちが愛した拓郎」(八曜社)124ページにも再録)の記事がある。
インタビュアー小倉エージの「1曲目の「この指とまれ」なんてそういう感じの曲でしょ」と問われた拓郎は
「完全にね“ハンド・イン・ハンド”はもうやかましいっていう気になってるんですよね」
「もうお先にちょいとゴメンしたいって言う曲、あれは」
と答えている。
もうひとつ「新譜ジャーナル」1982年6月号のインタビューにはこんなくだりがある。
吉田・・・アリスの"ハンド・イン・ハンド"(略)オレは嫌だったんだけど(略)関心はあったから歌にもなったよな。
----「この指とまれ」ですか?
吉田 まぎれもなく、そうだよな。
しかし拓郎は前記のとおり"この指とまれ=ハンド・イン・ハンド"を否定した。そのうえで2019年のライナーノーツで拓郎が語ってくれた”この指とまれ”の誕生経緯は深い苦悩に満ちた根源的なものだった。
僕は当時会社を作ったりする事に参加し徒党を組んで
自分らしからぬ日常に溺れるように入り込んで行った自分では気がつかなかったが、
もともと僕らは一匹狼的な生き方で音楽会に殴り込んで行ったはずであった
気がつけば組織の一人としての役割を何の抵抗もなく自ら担いながら
自分本来の進むべき道を見失ったままその事を誇らしく語ったりしていたのだ
「これはマズイ」と思ったとしてもまさに自然の成り行きだったのだろう
「そこからの逃れ」さすがに負い目も感じながら正々堂々とは言えぬ気分ながら
「抜けさせていただきたい」とあれやこれや・・複雑な事情が絡み合って
自分でも「どうすりゃーいいんだ」としかし時計は勝手にどんどん進むし
不甲斐ない自分にも腹は立つしそんな中で生まれたのが「この指とまれ」
身の置き所のないような悲しみに満ちた切なる告白だ。これを読んで思い出したのは、1981年の春「この指とまれ」が発表・初演された夏の体育館ツアーの準備中のことだ。拓郎はラジオで日常苦しめられている正体不明のストレスのことを語り、さらに「今度の夏のツアーには来ておいた方がいいと思う。なぜなら秋のツアーが危ない(笑)、最後になるとはいわないが、理由は・・・僕の気分がすぐれない。」と少し冗談めかしながらも不穏な発言をした。
その言葉どおり、体育館ツアーは素晴らしい完成度のもとに大成功したが、その後、チケットが一部発売され始めていたにもかかわらず秋の全国ツアーの全公演がキャンセルされた。その原因とおぼしき「すぐれない気分」とは何だったのか。具体的には明らかにされず謎のままだった。
今にして思えば、このライナーノーツの心情こそが、81年の拓郎にたちこめていた、コンサートツアーをすっ飛ばすほどの”すぐれない気分”と時期的・内容的に符合する。そうだったのか。所詮、思い込みにすぎないしても、ひとつの答えを得た気がする。
"一匹狼の自由な音楽家であること"と"企業組織の責任者であること"との矛盾相克する苦悩。2019年のラジオでもこの作品に関して「一匹狼が徒党を組んではいけない」(ラジオでナイト第95回)と語った。この行き場のない孤独な苦悩の化学変化こそが"この指とまれ"を生んだいうことになる。
「そういうところに居たくない、違うところに先に行っちゃいたい」(前掲「ミュージックマガジン」のインタビュー)という孤独な煩悶は、当時の拓郎を取り巻く社会現象のハンド・イン・ハンドやシアターフレンズ運動にもピタリとあてハマる。しかしそれらはあくまでこの作品の単なる一つの適用事例・エピソードであり、化学変化を助ける"触媒"のようなものにすぎない。この作品の出自はそんな薄っぺらなものではなく、一匹狼の音楽家としての魂の懊悩こそが生み出したものである。そのことを訴えんがための「断じて!ない!」だったのだと今は思える。
そして何より大切なことは、たとえ身の置きどころがないような苦悶の中にあっても、自分の懊悩をこれだけのクオリティの名曲に昇華させる吉田拓郎の一匹狼の音楽家としての力量である。奇しくも同じミュージックマガジン1982年1月号の「無人島で…」のレコード評に「自分の迷いを音にしないだけボブ・ディランより吉田拓郎の方が素敵である」とあるとおりだ。
それから幾星霜、その孤独な道ゆきのひとつの終着点とも思える2019年に久々に登場した"この指とまれ"は、ボーカルも演奏もそれはそれは素晴らしかった。“他の人のソロが終わるまで待つんじゃなくて、折り重なるように絡むんだ”という拓郎の心震えるような指示のもとのソウルフルなソロ回しが展開された。この作品が、あらゆるシガラミから自由になるための熱き名曲として今も生きつづけていることを証してくれた。
それにしても、この顛末からも浮かんでくるのは吉田拓郎のどうしようもなく孤独な道ゆきである。あなたはどうしてそんなに頑なに独りでゆかんとするのだろうか。ともかくその孤影悄然とした後ろ姿を見失わないように、耳を澄まし目を見張り、我もゆく心の命ずるままに。
2019.8/15