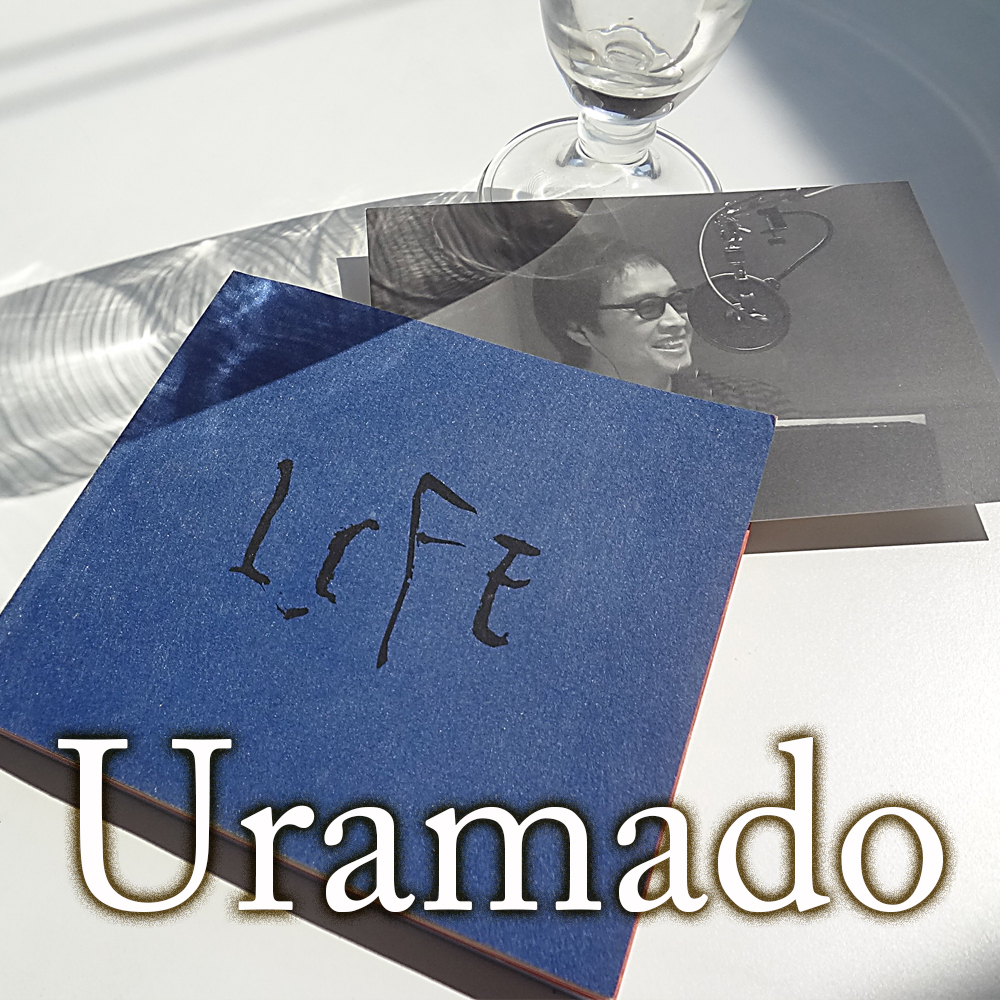心が届いた
作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎
アルバム「FOREVERYOUNG」
心に届く悲しき咆哮
80年代の最高アルバムと評される「FOREVER YOUNG」。このアルバムにはどうしようもない悲しみがそこここに溢れている。だからこそ最高のアルバムなのか。1984年。執拗に「過去の拓郎」を求め続けるファンとのすれ違いが拓郎を苦しめていたに違いない。当時拓郎は「コンサートツアーにも歌うことにも飽きてしまった」と言い放ち、それでも「ジョンレノンに敬意を表して彼が亡くなった40歳までは歌う」と口癖のように語っていた。「あとアルバムは何枚、ステージは何本」とカウントダウンをしながら、拓郎の心の中では既に翌年の85年のつま恋を最後のステージとした「現役撤退」のレールが敷かれていた。
そして時期を同じくし伴侶・浅田美代子との別れ。拓郎は、行き止まりのようなやるせない悲しみの中、ひとりぼっちで当てのない旅に出る前夜だったのだろうと思う。
一方、80年代前半の怒涛の音楽活動を経てバンドの熟練度は頂点に達していたことは誰もが認めるところだろう。やるせない悲しみと最強のバンド・・この対極の中に生み出されたのが、このアルバムだと思う。
さて、この作品。申し訳ないがやや印象が薄い。ただ楽曲の完成度は素晴らしい。王様バンドの真骨頂というべきサウンドはどこまでも力強く最強だ。ブラスも入って、ドラムのビートが砲撃のようにズンズンと響く。しかし、一見パワフルな印象のこの作品だが、詞で語られている本人自身の心情はとても切なく、ある意味で荒みきったものだ。このミスマッチがかえって作品全体としての印象を捉えにくくしているのだろうか。
「僕には今何も見えやしない。僕の眼に映るものはといえばドシャ降りの雨の音くらい。」 絶望的なフレーズだ。そのうえで拓郎は「僕には心も残っていない」とまで歌うのだ。「そして僕の体は木の葉のように舞う」・・はかないリフレインで作品は終わっていく。
元気に歌っているようで、実は「流れる」に漂うような悲しみと諦めの言葉たち。当時の行き場のない拓郎の心情が痛すぎるくらいに現れている。勝手な憶測だが、この作品は、傷心の拓郎が自分で率先リードして作られたというより、むしろ鉄壁のバンドに牽引されて作られたのではないか。大袈裟にいえば屈強なバンドに両脇を抱えられるようにしてかろうじて元気を見せて戦っているような気がしてならない。どこか悲しい咆哮のように聞こえる。
2016.1/9