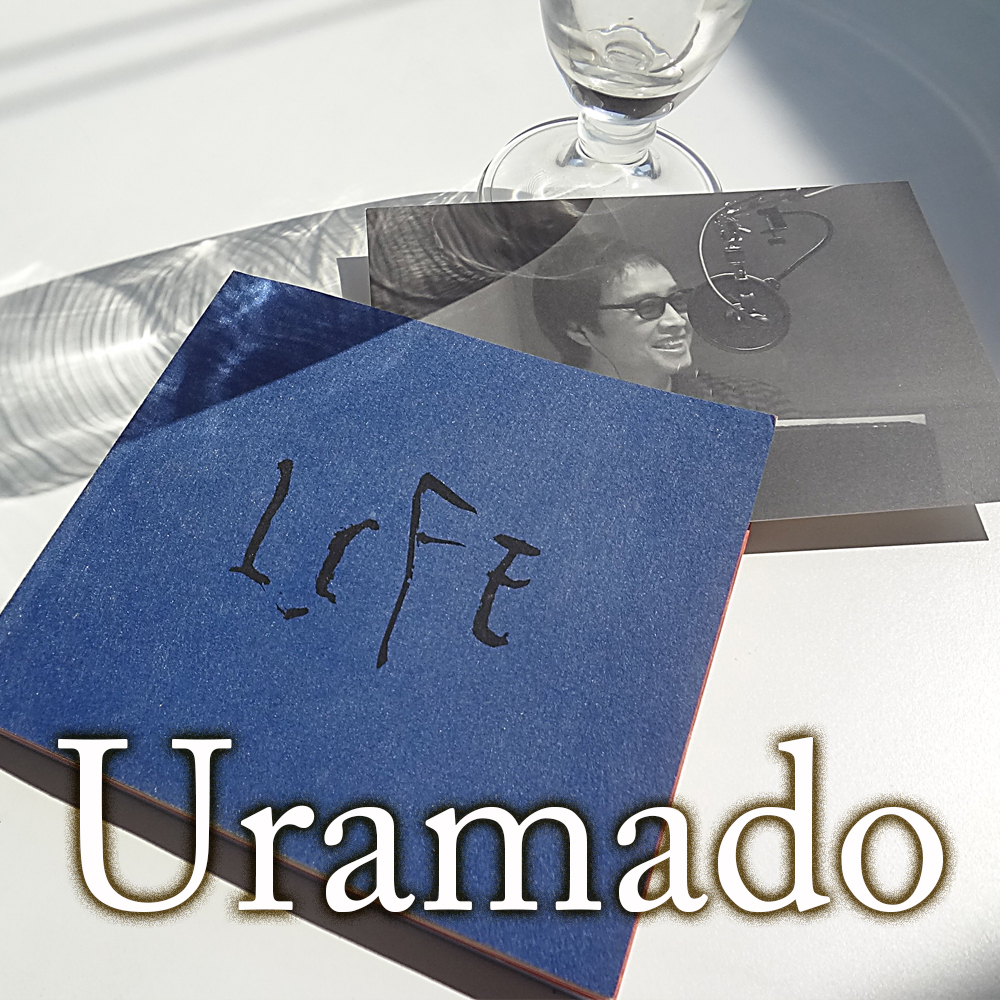僕を呼び出したのは
作詞 石原信一 作曲 吉田拓郎
アルバム「吉田町の唄」 」
若き日の残酷と歳月のねぎらい
名盤アルバム「吉田町の唄」の最後をしめくくるこの作品は、石原信一の作詞による静かなる名曲と言っていい。とにかく聴いていると、それぞれの昔日に思いが交差して、たまらない気分になってくる。他のファンの方からも同じような感想を聴くことが多い。
昔日の恋人との再会を歌った歌は数多い。その中でこの作品が特に胸を打つのは、人それぞれ状況や程度こそ違え、若き日の自分と自分の恋愛がいかに「残酷なもの」であったかという現実から逃げていないからだ。一般の唄によくあるように、耽美で淡いものでは決してなく、生硬で、身勝手で、荒廃し、意味なく傷つけ合い、破滅的だったりする、どうしようもない鬼畜なものであることを身もって知っているからだ。元ヤンキーが若き日のヤンキー自慢をするのとは違い、そんな恥に満ちた自分をしっかり封印しようとする。そんな人への共感のカギをこの作品は持っているのだと思う。
どうしようもなく、恥ずべき若い日の断片を「ささくれだったガラスの街を素足で歩き」「心の痣にウィスキー注ぎ倒れて泣けば」「失うものが何にもない」という適度に抽象化して描いている。抽象的な分、聴く人のそれぞれの思いの投影を広く受け入れてくれるかのようだ。特に「ムンクの叫び」に託し、中身を詳しく語らずに、別れの心情の表す描き方もイキだ。
拓郎にしてはあまり自己主張が際立たたない控えめなメロディーだ。しかし、それは、このドラマティックな詞を引き立たせながら、暗闇の中を光ある方向へガイドしていくような配慮あるメロディー展開であることに気づく。
陰惨な若き日の光景が切々と歌われたあとに、まるで深く息をつくように「残酷な季節だったと」とBメロに入る。そして、「風の中思い出してたぁぁぁ↑」「光るのは指輪だろうか 眩しくて顔を背けたぁぁぁ↑」というように、メロディーと歌唱がUPしていくところの爽快感。そのまま「少しはぐれたけれど今日まで生きてきたよ」という雲間から陽がさしくるようなCメロの展開。この拓郎のメロディー構成も大切な何かを「語って」いる。
メロディーが語ろうとしたことのヒントは、拓郎の言葉にあるのではないか。拓郎は、アルバム「吉田町の唄」の作詞依頼の時に「ねぎらい」という言葉を石原信一に投げかけた。「いろいろなことがあったが、ともかくオレたちはよくやってきたじゃないか。それを斜めでなく、しっかりと振り返って、明日へ進もう」という趣旨の「ねぎらい」が隠しテーマだったという。若き日の思い出と再会の胸キュンな感動ではなく、自分の過去への「ねぎらい」が、この詞とメロディーを彩っているに違いない。そう思ってもういちど、わが身に引き寄せこの作品を聞き直してみよう。
忘れ去られたような印象の作品だが、アルバム発表当時、ファンクラブT’Sの電話情報案内(ネットもない当時このアナウンスでいろいろな活動情報を得たものだ)のバックグラウンドには、「夕映え」とこの「僕を呼び出したのは」が流れさていた。きっと自信作だったに違いない。
ライブでも未演だが、つま恋2006の時、1週間前に泊まり込んでいたファンが、スタジオの壁に耳を当てて、かすかに立聴きしたところ、リハーサルはしていたらしい。くぅぅぅ、そこまで近くに来ていたのか。「花の店」「朝陽がサン」を繰り返し歌うのであれば、こっちも一回でいいから歌ってくれまいか。
2016.1/9