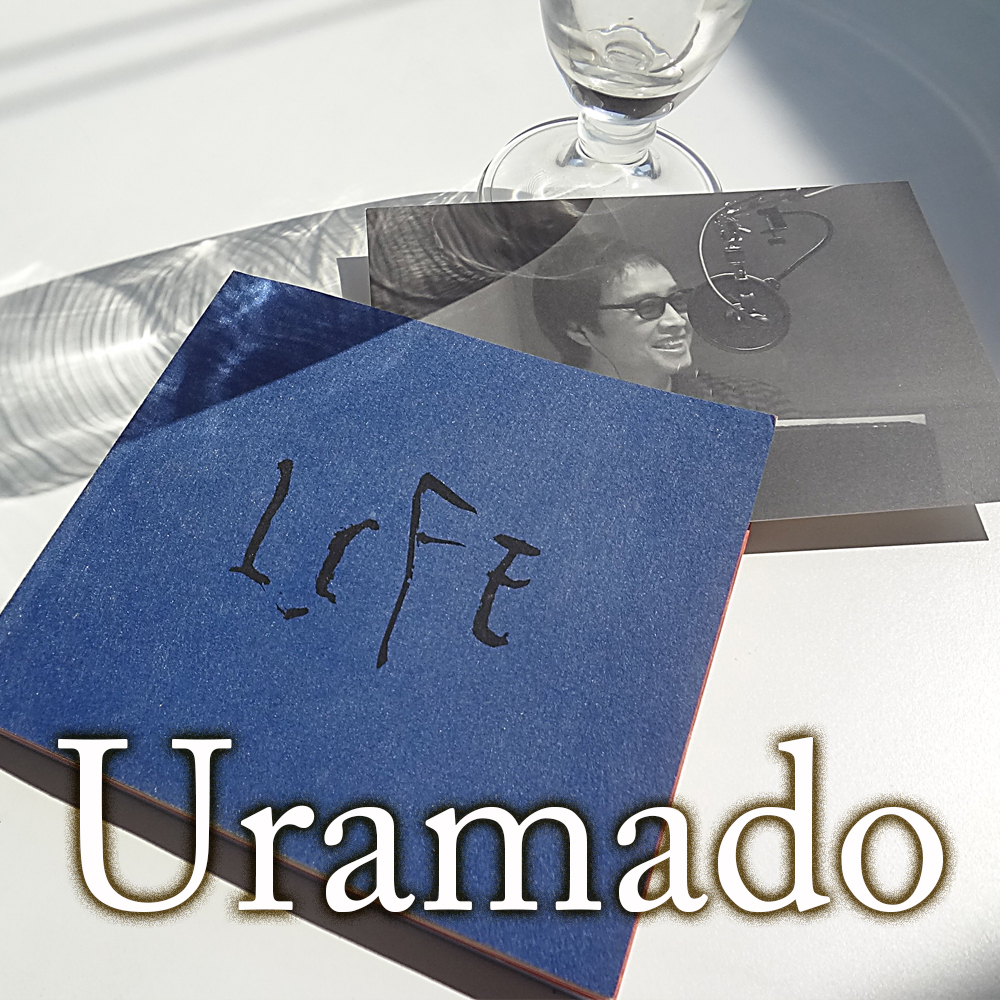To the Moon
作詞 石原信一 作曲 吉田拓郎
アルバム「Long time No See」
コンピュータという大いなる布石に
この作品に限らず石原信一の詞は、老いや衰えという高齢化現象きっちりと描く詞が多い。この作品も「胃薬」「ほどほどの暮らし」「家族とは諍いを避けて」「目立たなく生きる術」など・・おじさんの愚痴にしかならないようなスレスレの詞だ。そこを拓郎が歌うと、このおじさん臭漂う詞に、なんとも言えない輝きが宿る。歳をとることも悪くないかなと言う気がしてくる。これが石原との共作のツボだ。
かくしてこの作品もアルバム「Long Time No See」の中で最も軽快なロックナンバーとして生きている。バハマでの、ラス・カンケル、クレイグ・ダーギーら外国の一流ミュージシャンたちとのセッションだが、仕上がりは実に拓郎らしさに満ちている。
80年代後半から、コンピュータ打ち込みに走ったりして迷走を続け、ファンの不興を買い、本人曰く「彷徨っていた」という冬の時代の拓郎。そのさまよえる拓郎が、音楽的な突破口を開いたのが、このバハマでのセッションだ。これまで、海外録音はロス(「シャングリラ」)もニューヨーク(「サマルカンドブルー」)もどこかリラクタントだった拓郎は、この三度目のバハマの海外録音にして初めて開眼したかのようだ。
それは参加したミュージシャンが素晴らしかったからだと言われるが、本当の原因はそれだけではない。今回は、拓郎が彼らミュージシャンをきちんとコントロールできたという点にあると思う。それは2009年のツアーパンフのインタビューでわかる。
それまでの海外録音について拓郎は「名うてのミュージシャンがいるけど僕の意見は無いわけだよ。」とある種の疎外感があったことを語った。
しかし、バハマでの拓郎は、事前に、コンピューター打ち込みの熟練した技術によって「完璧なデモテープ」を制作して臨み、ミュージシャンたちを驚かせた。これを聴かせて、自分の描く音楽を明示し、納得させ、唸らせたという。こうして拓郎が、海外のミュージシャンたちを制圧し、コントロールできたからこそ、拓郎自身の音楽的充実と作品のクオリティが確保されたのではないか。
この拓郎の音楽的リーダーシップによって、技術的意味だけでなく、これらミュージシャンとの音楽的信頼感が生まれ、まるで王様バンドの時のような結びつきで、コンサートツアーまで挙行されたことは記憶に新しい。って、もう20年前だよな。
かつて多くのファンをトホホな気分にさせ、ファン離れを加速させたコンピュータ打ち込みは、ここで実に大きなチカラを発揮したのだった。やはり拓郎の言動を近視眼で観てはならないという教訓だ。時にファンも長き風雪に耐えてこそやがて味わえる境涯があるに違いない。
2015.11/29